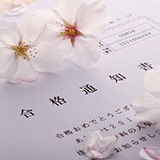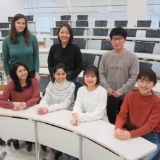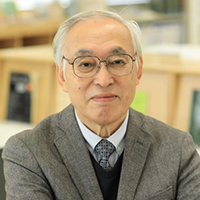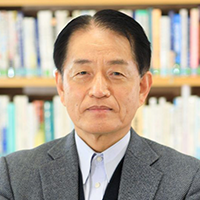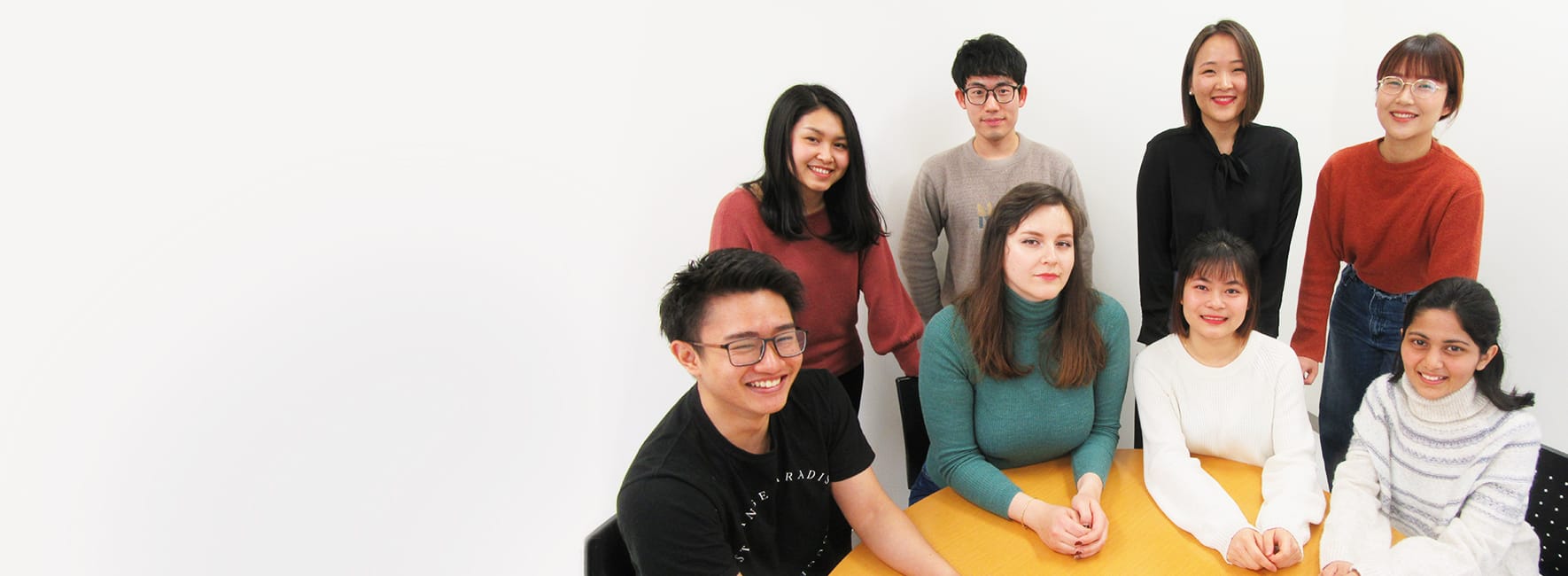「科目免除」という選択肢で
“企業の将来ビジョン”を経営者と共に描ける
「税理士×MBA」を目指す
税理士業界の現場では、企業のクライアントから様々な分野・領域での専門的なアドバイスやコンサルティングが求められています。税理士業務は、単なる財務や税務に関する過去の業績等を数値化するだけではありません。
「設立」・「株式公開」・「再生」といった企業の成長過程において、蓄積されたデータをもとに企業の成長・発展を支えるためのアドバイスや、幅広く経営全般にわたる具体的な経営コンサルティングが期待されています。また、税理士を取り巻く環境は年々複雑化・多様化し、税理士に期待されるサービスや仕事の領域は、より高度になり、専門化してきています。
事業創造大学院大学では、このようにクライアントの多様なニーズに応えるために経営者目線に立ち“企業の将来ビジョン”を共に描ける税理士を輩出するべく、「科目免除」という選択肢で税理士資格取得を目指します。
本学修了時には、経営学の修士号である経営管理修士(専門職)MBAの学位が授与されるため、試験合格では得られない専門性、独立・起業ノウハウが養われます。またビジネススクールならではの多様な人材との異業種交流・ネットワークの構築が可能です。